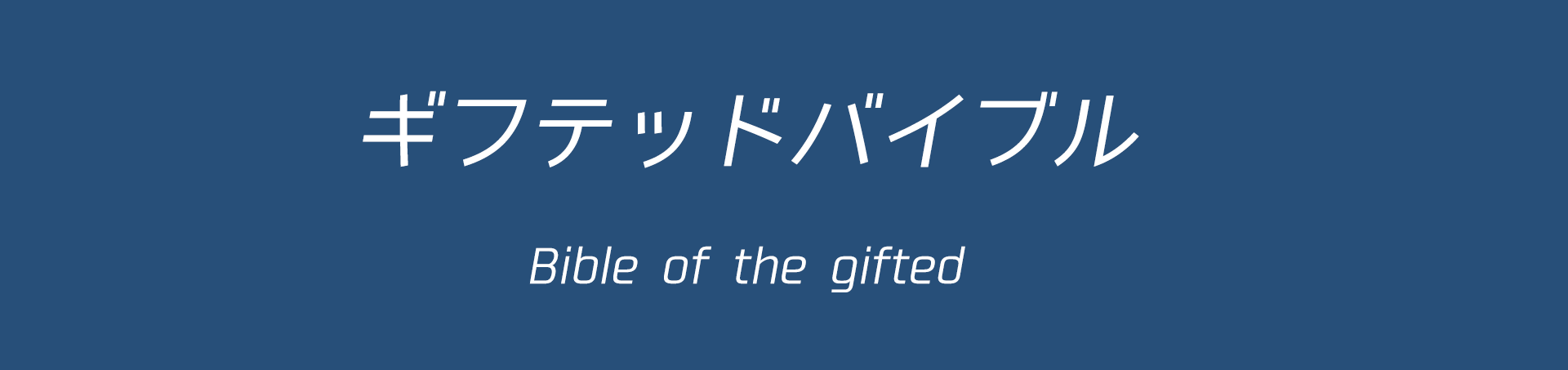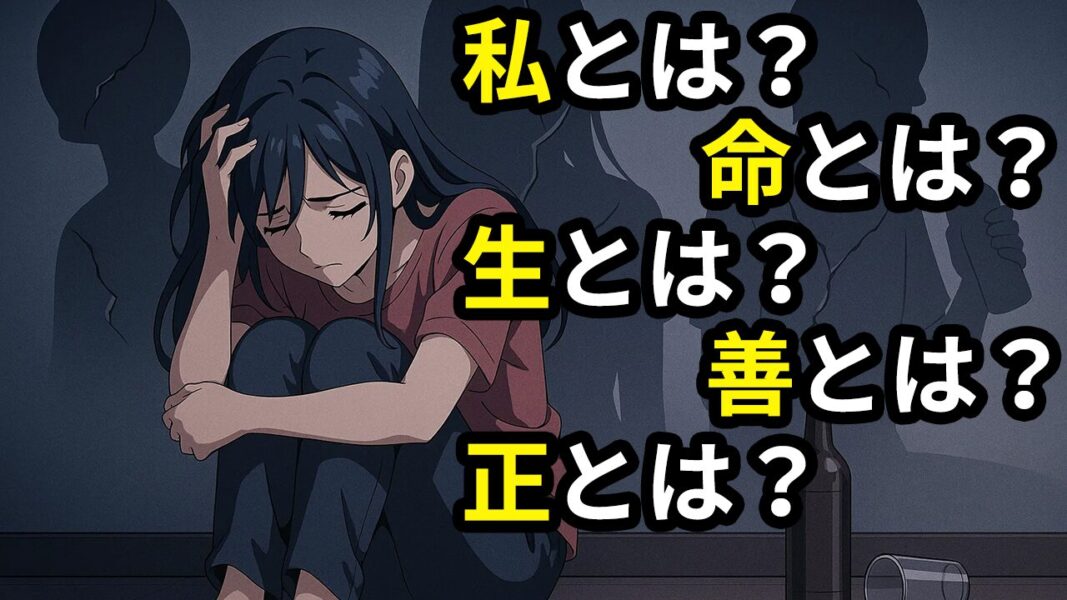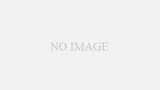アイデンティティクライシス対策における根底にある哲学的な視点と実践的なアプローチについて、詳しく説明します。
アイデンティティクライシスとは?
まず、アイデンティティクライシスとは「自己喪失」とも呼ばれ、「命って何だろう、生きるって何だろう、人生って何だろう、自分って何なんだろう、生きていくことってどういうことなんだろう、善悪って何だろう、正しいとか間違ってるって何だろう」といった思考をぐるぐる繰り返してしまう状態のことです。これは、自己同一性(アイデンティティ)という、自分が何者なのかという自覚や解釈が喪失し、危機的状況に陥っている状態です。具体的には、意識や認知、価値観の座標、つまり地図や羅針盤のような指針が曖昧になり、何について思考すれば良いかを見失っている状態です。
ギフテッドはアイデンティティクライシスを起こしやすい
ギフテッドと呼ばれる、何かしらが突出している人はこの自己喪失に陥りやすい傾向があります。これは、思考について思考する能力であるメタ認知能力が高いことが引き金となっています。ギフテッドは、論理的推論能力や空間認知に依存するメタ認知能力が秀でており、その能力が逆に障害となりやすいため、自己喪失を起こしやすいのです。
アイデンティティクライシスを起こすことは、一見ネガティブに思えますが、ソースでは「希望」であると述べられています。なぜなら、思考の羅針盤がないまま行動してしまうと、現実で痛い目を見てしまうことが多いのに対し、自己喪失を起こして行動できない状態は、ダメージを最小限に抑えられるという希望だからです。何もわからないまま行動する人よりも、傷が浅く済み、対策を知れば傷を負わずに起死回生できる可能性があるため、アイデンティティクライシスは希望なのです。
アイデンティティクライシス対策3ステップ
このアイデンティティクライシスの対策には、主に以下の3ステップがあります。
- 不二一元論(梵我一如)
- リソース&キャピタル(ヒューマンリソースとヒューマンキャピタル)
- マインドフルネスとファクトフルネス
これらの対策は、アイデンティティクライシスの根本原因である「価値観の矛盾」を紐解くためのものです。これまでの人生で努力して「良い」とされるものを手に入れたり、目標を達成したりしたにも関わらず、心の空洞が埋まらないと感じる燃え尽き症候群のような状態が、自己喪失に繋がることが多いのです。世の中で「良い」とされている価値観が、実際に手に入れてみると自分の心の空洞を埋めなかったという矛盾が、アイデンティティクライシスに繋がります。
ステップ1:不二一元論
不二一元論は、別名「梵我一如(ぼんがいちにょ)」とも呼ばれます。これは、「梵」(宇宙、摂理、法則、森羅万象)と「我」(人間、意識)が不可分であり、一つであるという考え方です。
この考え方は、私たちが普段「自分」だと思っている「意識」が、実は体や心といった、命(仕組み)の中では、非常に薄い表面的なものであるという洞察から始まります。人間は1日に約3万5千回の選択と決定をしていますが、そのほとんどが無意識で行われています。心臓の鼓動や血流、ホルモン分泌なども意識的にコントロールしているわけではありません。意識は、主観的には日常をコントロールしているように感じますが、実際には自分の心や体、命そのものの「仕組み」に直接的な影響を与えることは絶対にできません。
そして、意識そのものが「自分」であるという結論に至ります。意識があるかどうかの違い(起きているか眠っているか)で、同じ8時間でも体感が全く異なることなどがその例です。意識は体や心、命に影響を及ぼせない薄いものですが、それが自分なのです。
さらに進んで考えると、自分という意識があってもなくても、体は生き続けるし、大統領や有名人がいなくなっても世の中は何ら滞りなく回ります。偉大な人ですら世の中の歯車の一つに過ぎません。このことから、個人が「いてもいなくてもいい」という真実に気づくことが重要であると述べられています。
アイデンティティクライシスは、そもそも自分というものを過大評価し、主観の大きさを大きく見積もりすぎていることから始まっています。不二一元論を通して、「自分は意識であり、意識は全体の命に影響を及ばせない、いてもいなくてもいい存在である」という真実を知ることが、その過大評価を是正する第一歩となります。
「いてもいなくてもいい」ということから「自分には価値がない、死んでもいい」と考える人もいますが、ここで重要になるのが次の存在価値と付加価値の話です。
ステップ2:ヒューマンリソース&ヒューマンキャピタル
このステップでは、存在価値と付加価値の違いを理解することが重要です。経済学の「資源(リソース)」と「資本/資産(キャピタル)」に例えて説明されます。
- リソース(資源):限りあるもの、有限なもの、使うと減るもの、増えにくいもの。人間にとってのヒューマンリソースは、体、心、時間、そして(ある側面では)お金です。これらは「存在価値」に相当します。使ったら減り、無くなったら死に至るため、この存在価値を目的とすべきなのです。これは「絶対価値」とも言え、代わりが効きません。
- キャピタル(資本/資産):減らない、積み上げていくもの、積み上げると減りにくいもの。人間にとってのヒューマンキャピタルは、経験、学習、スキル、知識などです。これらは「付加価値」であり、「相対価値」です。代替手段があり、代わりが効きます(例えば、自分が料理を作らなくても、コンビニや外食で済ませられるように)。
現代社会では、この付加価値(相対価値/キャピタル)を重視しすぎ、付加価値しか見ていない傾向があります。仕事やお金、愛情、夢、希望、健康といった付加価値は、存在価値(絶対価値/リソース)という巨大な土台の上に成り立ちます。しかし、多くの人がその土台である存在価値を蔑ろにして付加価値を目的としてしまうため、順番が逆になり、存在価値が危うくなってしまいます。体が壊れたり、心が壊れたり、時間が無くなったりして、「どうやって生きていけばいいか分からなくなる」という状態に陥るのです。
不二一元論で述べられたように、人間は宇宙の法則と同一であり、いてもいなくてもいいと捉えることもできれば、最も重要なものと考えることもできます。これを踏まえると、付加価値よりも存在価値を重視すべきであり、存在を最優先で考えることが、クオリティ・オブ・ライフを高めることに繋がります。
存在価値と付加価値、相対価値と絶対価値を混同していることが、生き方に迷い、価値を見失う原因となり、それがルッキズムやカテゴライズといった現代社会の諸問題に繋がり、ひいては付加価値を目的にした結果、自尊感情が失われて自己喪失に至るという流れがあります。そして、自尊感情の欠落や矛盾は、攻撃性となり、犯罪や自殺、差別、偏見、戦争といった問題の根本原因に繋がっていくのです。
ステップ3:マインドフルネスとファクトフルネス
存在価値を大事にする生き方、つまり「存在をよりよく存在させ続ける、存在を高めていく、存在を使っていく、存在価値を知っていく」という生き方が最適化であると述べられています。そのために、以下の2つの考え方が重要になります。
- マインドフルネス:これは「今この瞬間に集中しよう」という心の組み方(マインドセット)です。生まれてから死ぬまで、私たちは常に「今」を生きています。過去や不確かな未来、他者の心などに時間を使いすぎると、存在価値であるリソースを消耗してしまいます。マインドフルネスは、この「今」という時間の価値を最大限に活かす考え方です。生きている1秒の価値は全宇宙の財宝に勝るほど貴重であり、その「今」を無駄にしないために、今というものの重要さや価値に意識を向けることが大切です。
- ファクトフルネス:これは「真実をちゃんと見ましょう」という心の組み方です。真実ではないことを真実だと思うことが「矛盾」であり、その矛盾が人間社会におけるあらゆる問題の根本原因であるとソースは述べています。アイデンティティクライシスも矛盾が根本原因であり、自尊感情の欠落によって生じます。存在価値は究極に価値があるものであるにも関わらず、自尊感情が欠落すると「自分なんて価値がない」と思ってしまうという矛盾を抱え、それが悩みや苦しみ、攻撃性に繋がっていくのです。
ファクトフルネスは、自己最適化(自分自身の体、心、時間、お金といったリソースをより少ないコストでより多くのリターンが得られるように最適化する生き方)や環境最適化(リソースを無駄に減らさず、増やせるような人物、こと、場所を選択すること)を加速させるために必要です。
特に、自分の能力や価値を正しく認識することが重要です。自己卑下や謙遜しすぎることが、ファクトフルネスができていないことに起因することがあります。例えば、英語が話せる能力や、料理や家事といった日常の能力、スポーツやアウトドアの能力など、多くの人ができないことができるのに、「大したことない」と思ってしまうのは、全体の中での自分の立ち位置や能力の価値を数字や統計的な視点で見れていないからです。真実を見ることで、どんな状況にあったとしても自分の価値がなくならない、自尊感情を失わない、存在価値を危うくさせないという希望に繋がります。
まとめ 価値を見直して自己を最適化してから環境を最適化しよう
アイデンティティクライシスの対策の根底にある哲学的な視点は、不二一元論(梵我一如)に基づく「存在そのものが価値である」という絶対的な真実であり、実践的なアプローチは、その真実を踏まえ、存在価値であるリソースを最重要視する生き方を自己及び環境において最適化していくことであり、そのための具体的な心の組み方としてマインドフルネス(今を大事にする)とファクトフルネス(真実を見る)を用いることと言えます。
これらの対策は、アイデンティティクライシスを解決に導く可能性があり、一度だけでなく繰り返し聞くことで、より深く腹落ちし、実践に繋がると述べられています。