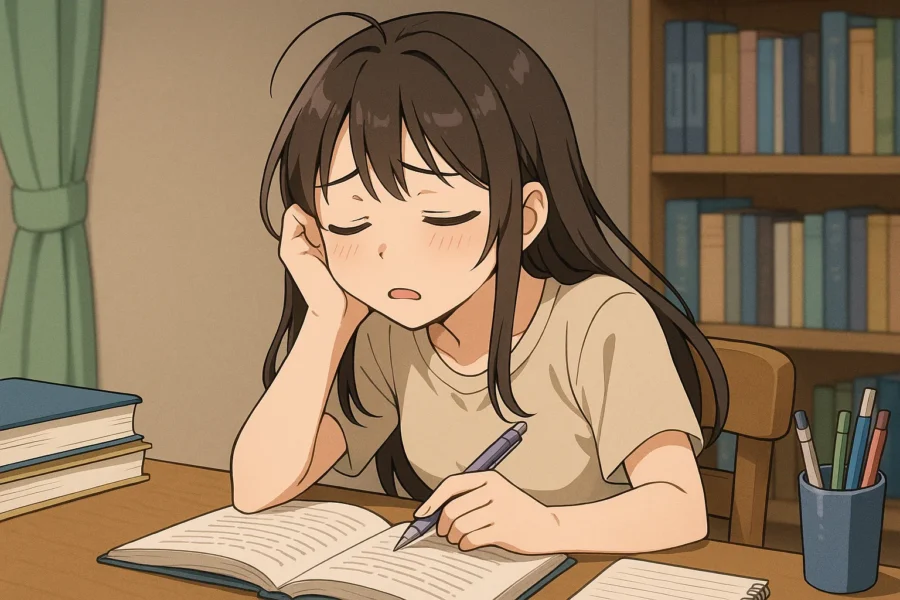~ギフテッドが抱える“焦燥感”と“ドーパミンの罠”~
すぐに飽きる、続かない。それって「病気」?
「やる気が出ても、3日も続かない」「新しいことを始めても、気づいたらやめている」
こんな自分にうんざりして、「自分ってなんて根性なしなんだろう…」と悩んだことはありませんか?
もしあなたが、
・頭の回転が速いと言われる
・感情や感覚が人よりも強い気がする
・周囲のことを察しすぎてしまう
・常に何かを探しているような気がする
そんな傾向があるなら、それは単なる「わがまま」や「飽きっぽさ」ではなく、**ギフテッド(またはその特性を持つ人)**特有の「神経の過敏性」や「認知特性」が関係している可能性があります。
本記事では、
忍耐力が続かない本当の理由と、
どうすれば“途中で投げ出さずにいられるか”
について、脳科学・心理学・発達特性の観点からわかりやすく解説します。
なぜ「続かない」のか?原因をひも解く
Overexcitability(感情・感覚の過敏性)
ギフテッドの人がよく持つ特性に「overexcitability(オーバー・エキサイタビリティ)」というものがあります。
これは、日本語で言うと「過剰興奮性」。
つまり、五感・感情・思考・想像力などの反応が、平均よりずっと強い、ということです。
例えば、
・ちょっとした騒音が耐えられない
・すぐに不安になったり怒ったりしてしまう
・他人の感情にすぐ共鳴してしまって疲れる
・些細なアイデアでも“全体像”まで一瞬で妄想してしまう
など、刺激に対して「耐える」前に、もう頭がフル回転して疲弊してしまうのです。
この状態で「忍耐」しようとすれば、当然ながらものすごくエネルギーを使います。
人一倍がんばっていても、「なんで続かないの?」と思われるのは、とても苦しいことです。
新奇性追求性と“飽きっぽさ”
ギフテッドの多くは「新奇性追求性」という性質もあわせ持っています。
これは、新しい刺激を求めてしまう性格傾向で、「次、次!」と常に目新しいものへと興味が移ってしまいます。
退屈が「苦痛」レベルに感じられるため、
ちょっとでも慣れてしまうと「次の刺激が欲しい!」という状態になります。
この傾向は、脳内の「ドーパミン」と関係しています。
ドーパミン受容体と“続けられなさ”の関係
ドーパミンってなに?
ドーパミンは、脳内で分泌される「やる気」や「快楽」に関係する神経伝達物質です。
何かを成し遂げたとき、「やった!」と感じるのは、ドーパミンが放出されているから。
ただし、ギフテッドに多いとされる「新奇性追求型」の人は、このドーパミンの「受容体(レセプター)」の感度が低いことがあります。
つまり、普通の人よりもドーパミンの“快感”を得るために、より強い刺激や成果を求めてしまうという状態です。
これが、何かを継続しようとするときに、
- 「すぐに成果が出ないと耐えられない」
- 「途中の地味な過程が苦痛」
- 「先が見えないと投げ出したくなる」
といった“忍耐力のなさ”につながってしまうのです。
スクラップ&ビルドを繰り返す思考パターン
ギフテッドの中には、自分の価値観や信念、行動スタイルを定期的に壊しては作り直す「スクラップ&ビルド型」の人も多くいます。
これは一見、柔軟で創造的なように見えますが、
本人にとっては「定着しない」「育たない」「安定しない」といった“焦燥感”の原因になることがあります。
目の前のことに耐えて取り組むよりも、
“より良い形に作り変える”という選択をしてしまう。
結果、「忍耐力が続かない」という状態になりやすいのです。
「演繹的思考」と「先見の明」が妨げる“行動の継続”
演繹的思考とは?
演繹的思考とは、「原理や前提から具体的な結論を導く」思考法です。
たとえば、「AならばB、BならばC、よってAならばC」というように、筋道立てて物事を考える力。
この思考力が高い人は、物事を始めたときに「これってどうせこうなるよね」という未来の結末が、スタート地点で既に見えてしまうという特性を持っています。
先見の明が「やる前に飽きる」原因に?
一般的には「先見の明があるのは素晴らしいこと」とされます。
ですが、ギフテッドのように情報処理速度が速く、全体構造を短時間で予測できる人は、行動の途中にある“細かい積み重ね”に意味を見出せなくなることがあります。
- 「これは成功するけど、リターンが小さい」
- 「この手間をかける価値はない」
- 「この分野はもう伸びしろがない」
というように、冷静な“合理的判断”が、感情や熱意を上回ってしまうのです。
だからこそ、せっかく始めたことも「やる意味ある?」と途中でやめてしまいやすくなります。
これが、周囲からは「飽きっぽい」「持続力がない」と誤解される大きな要因です。
セルフスティグマが引き起こす“自己否定のループ”
セルフスティグマって?
「セルフスティグマ(Self-stigma)」とは、自分で自分に対して偏見を持ってしまうことを指します。
たとえば、
- 「またすぐやめた…自分ってダメなやつ」
- 「他の人は続けてるのに、なんで自分は…」
- 「自分はどれも中途半端で終わる人間だ」
こうした思考は、失敗経験や過去の挫折から学ぶ代わりに、「自分はこういう人間だ」とラベルを貼ってしまう心の防衛反応とも言えます。
けれどこの自己否定は、次のチャレンジにもブレーキをかけるようになります。
忍耐力は「自信」の上にしか積み上がらない
「続ける力」は、“できた”という小さな成功体験の積み重ねによって育ちます。
しかしセルフスティグマによって自信が欠けていると、失敗の予感のほうが強くなり、始めること自体が億劫になってしまうのです。
つまり、忍耐力を育てるには、
まず「自己否定をやめること」が先なのです。
忍耐力を「持てる人」になるためのヒント
では、どうすれば「すぐにやめる」状態から抜け出して、「続けられる人」になれるのでしょうか?
1. “外側の目標”ではなく“内側の報酬”を設定する
ギフテッドの多くは、達成感や他者評価では動けないタイプです。
むしろ、やらされ感や義務感があると、ドーパミンが出にくくなります。
だからこそ、「この作業は自分にどんな面白さをもたらすか」「どこで自分は“ワクワク”を感じるか」を自分で言語化しておくことが大切です。
外的な目標(資格取得・収入・評価)よりも、
内的な快感(気づき・深まり・美しさ)を意識しましょう。
2. 長期目標を“点”で捉えず、“線”として見る
「ゴール」を絶対視してしまうと、「そこに届かない限りは失敗」という思考になりがちです。
これは、演繹的思考や完璧主義の人にありがちな罠です。
ですが、何かを「続ける」ということは、むしろ“変化の軌跡を味わう”旅です。
- 昨日はここまでできた
- 今日はここが分かった
- 明日はここが気になる
といった、「日々の変化」を可視化していくことで、継続の意味を“結果”から“過程”へとシフトできます。
3. やめてもいい。けど「やめ方」は記録する
ギフテッドにとって、「やめること」自体は悪ではありません。
むしろ、判断が速いという強みでもあります。
ですが「なぜやめたのか」を記録しておかないと、
あとで「また途中で投げ出した」という罪悪感だけが残ります。
「この段階で飽きた理由」や「次に活かすならどうするか」を残しておけば、
それは“忍耐できなかった失敗”ではなく、“学びのある実験”になります。